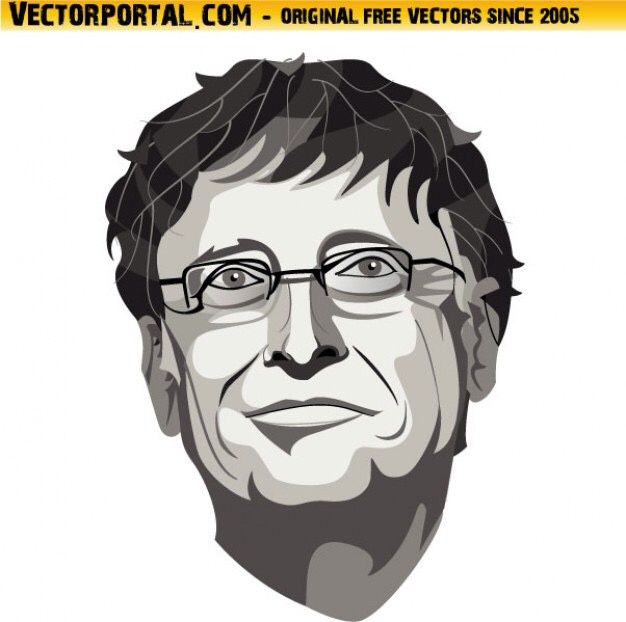サムスンが折りたたみスマホの第2弾を発売します。
なんと今回は縦折りのスマホ。
auが折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip」を2月下旬に発売することになりました。
こちらはau独占販売となります。
折りたたみと聞くと、ガラケーに戻った感じもしますが、折りたたみのまま電話が出来たり、とてもコンパクトでデザイン性に優れていたりと、とても魅力的になっているそうです。
名古屋オーシャン野球教室に通ってる子もスマホやタブレットを持っている子がたくさんいます。
少し前には考えられないことですね!!
今日はそんなスマホの色んな事情について調べたのでお伝えしようと思います。
AndroidとiPhoneの違い

OS(オペレーティングシステム)が変わると仕様も大きく変わる
AndroidとiPhoneに搭載されてるOSはそれぞれ異なります。
Androidは「Android」、iPhoneは「iOS」というOSが採用されており、OSが変われば、ボタンの配置や利用できるアプリなど、機能面も大きく変わってきます。
使いやすさは慣れでもあるが、もしかしたら今まで重宝していた機能が使えなくなってしまう可能性もあります。
OSごとの特徴
Android端末に搭載される「Android」は、Google社がLinuxを携帯端末用に改良して作ったOSとなっています。したがってホーム画面を自由に設定できたり、デフォルトのフォントを変更したりと、自分好みにカスタマイズすることができるのが特徴です。
それに比べてiPhoneが搭載する「iOS」は基本的にはデフォルトの制限がある中で利用するため、柔軟性には欠けています。しかし、現在Android勢であっても特にカスタムは重視していなかったり、デジタルに疎い方などはiPhoneが使いやすく感じるかもしれないと思います。
説明書がなくとも直感的に操作できる安定感があり、少し操作すれば割と誰でも使いこなせてしまうシンプルさが魅力です。
AndroidからiPhoneに乗り換えるデメリット

搭載OSによって仕様が変わるのは想定内ですが、デメリットが多くては本末転倒。AndroidからiPhoneに乗り換えると、具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。
①端末の値段が高い
Android端末の値段を基本に考えると、iPhone端末は高く感じるかもしれない。
Androidの「OPPO Reno A」や「HUAWEI P30 lite」の新しい機種でも40,000円前後、少し前の「ZenFone Max Plus (M1)」や「nova lite 2」はそれぞれデュアルカメラを搭載し、なかなかのスペックでありながら20,000円台で購入できます。
それに比べてiPhoneは現在最新モデルは10万を超えています。
格安SIMでiPhone6やSEを購入するのも術ですが、旧型でありながらiPhone SEで40,000円台、iPhone6で60,000~70,000円台と、SIM込みであっても格安とは言い難い値段です。
②マルチウィンドウが使えなくなる
マルチウィンドウはAndroidを利用している方ならおなじみの便利な機能ですね。通常1画面しか表示されないところ、「マルチウィンドウ」機能を使えば2画面同時に開くことができます。
画面の上半分で調べものをしながら下半分の画面でメモが取れたり、上部画面にYouTubeで音楽を流しながら下部で別の作業をすることができるなどとても便利な機能です。
iPhoneにもマルチタスクという、アプリを同時に開いておける機能は存在しますが、同時に2画面を表示することはできません。今表示されているアプリの裏で他のアプリを開いておき、タップで表示画面を切り替える仕組みです。
③使えるアプリが減る
Android対応のアプリに比べたら、iPhone対応のアプリは少ない。現時点でAndroidのアプリは143万種類あるのに比べてiPhone向けアプリは123万種類です。
AndroidはIOSよりも規定が少なく、開発したアプリの審査が通りやすいため、利用できるアプリの幅も広がります。個人のカスタマイズにアプリは必要不可欠なので、たくさんのアプリから選択できるのはありがたいですね。
④アプリが整理しづらくなる
iPhoneはホーム画面がアプリ一覧画面を兼ねているため、下部のよく使うアプリ以外は縦5つ・横4つのアイコンが並んで表示されます。
SNSやゲーム、写真加工など、アプリをジャンル分けしたい場合は、いくつかのアプリをひとつのアイコンに集約することもできるのだが、ドラッグ&ドロップでひとつひとつ動かすのも面倒です。
それに比べてAndroidはホーム画面から自分の使いやすいようにカスタムすることができる。
ホーム画面にはよく使うアプリのショートカットやウィジェットのみが表示され、アプリは別画面で表示するという仕様です。パソコンのデスクトップもきちんと整理する派ならAndroidの方が好ましいかもしれないですね。
iPhoneへ機種変更するメリット

①操作が簡単
iPhoneはなんといっても操作が直感的で簡単という強みがある。使い初めから操作で迷うことが少なくスマホデビューにも向いているため、説明書がないのにも納得です。
機能面でも玄人ほどのこだわりがなければ全く問題はないので、万人向けのバランスのとれた機種だと言えます。
②ストレスフリーなサクサク感
これは使用しないとわからないとわかりづらい部分ですが、iPhoneはタッチレスポンスの感度がよく、動作のサクサク感が素晴らしいです。
Androidは使い続けているうちにどうしても動きがモサっとしてきてしまうところが難点なのです。
③常に最新OSが利用できる
サクサク動作し続けられる点として、iPhoneは常に最新OSが利用できるという点が上げられます。
iPhoneは毎年大きいアップデートと、微々たる調整を繰り返して進化しています。
アップデートを怠ってしまうとサクサク感が損なわれたり、勝手に電源が落ちてしまうなどのバグが発生してしまうが、アップデートのお知らせがきたら素直に対処すれば問題ない。
一方Android端末を利用している方は、約4割が古いOSで使い続けているという衝撃のデータが出ています。iPhoneのOSはAppleが専門的に開発しているため自社のOS以外が搭載されることはなく、OSが進化すればすぐさま端末も対応できる。
しかしAndroidの場合は、OSはGoogle社が開発し、端末は別のメーカーが製造するため、その都度最新OSに対応ができずこのような事態が起きてしまいます。
④安心なセキュリティ
Androidは自由にカスタムでき、対応アプリが多い点が魅力だが、それだけアプリを発信できるのは、AndroidはiOSに比べてアプリの審査が甘いことが理由にあります。
多くのアプリを利用できるのはありがたいが、個人開発でGoogle非公式のアプリなどもダウンロードできるぶん、場合によっては不正なコードを持つアプリをインストールしてしまう恐れがあります。
不正アプリを落としてしまうと、インストール中に個人情報を抜かれることもあります。
まとめ
上記の他にもたくさんのメリット、デメリットがあります。
そもそもネット社会になっている現代社会でスマホ無しでは生きていけないと言う人もたくさんいると思います。
ネット社会の利便性に伴い、危険な一面もあるということは誰しもが知っておかなければいけないですね。
名古屋オーシャン野球教室に通っている子も知って使ってほしいと思います!!