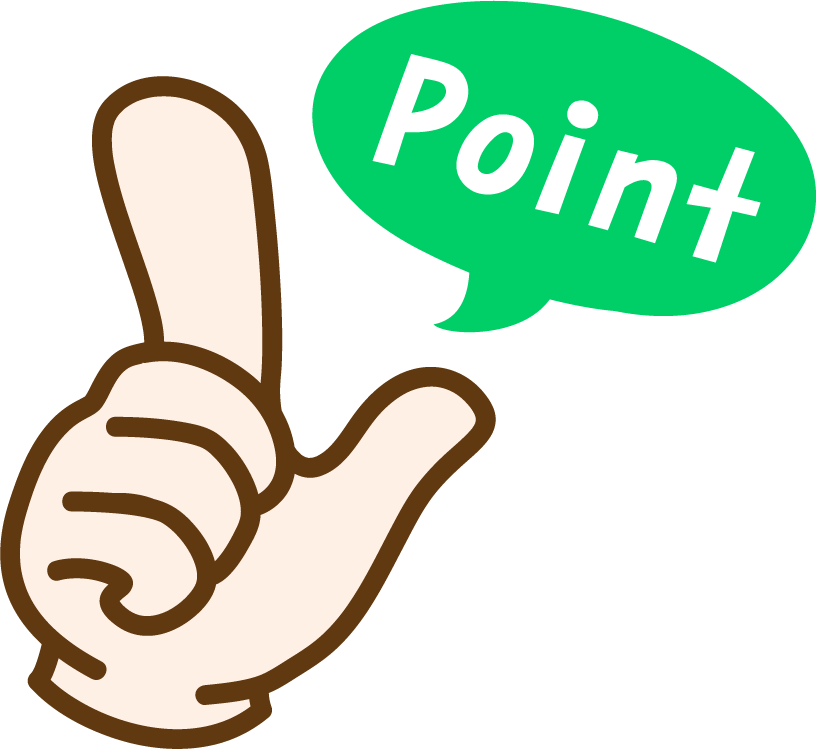スポーツを観ていて、「なぜこんなことをするのだろう?」と思うことはたくさんありませんか?たとえば、サッカーの試合で入場時に子どもと手を繋いで入場したり、レスリングの試合でハンカチを持っていたり。いろんななんでだろうがある中でもいちばんの疑問は、野球の監督はなぜユニフォームを着ているのか?ではないでしょうか?
他のスポーツでは、監督はスーツやジャージを着て指揮を執っているのに、なぜ野球だけユニフォームなのか?そこで今回は、野球の監督がユニフォームを着ている理由についてお話していきたいと思います。
名古屋オーシャン野球教室では、もちろんユニホームを着て指導します!そこにも、今回お話する中で同じ理由が含まれているかもしれませんね。
野球の監督はなぜユニフォーム姿なのか?野球の監督が着る服装にルールはない!

そもそも、野球規則には「選手は全員同じユニフォームを着ること」という規定はありますが、監督やコーチの服装に関するものは存在していません!!つまり、スーツやジャージを着ても何ら問題ないのです。それでは、たなぜユニフォームを着用しているのでしょうか!?これに関しては、いくつかの理由が存在しているようです。
選手が監督を兼ねることが多かったため
まず、野球はかつて専属の監督はおらず、選手が監督を兼ねることが多かったそうです。その影響から、監督もユニフォームを着ることになったとする説があります。いわゆる「代打、オレ」ってやつですね。日本でも野村克也や古田敦也などの選手兼監督が有名なだけに、これはかなり有力な理由ではないでしょうか。
監督がフィールドに出入りするため
また、ほとんどのスポーツでは、監督やコーチがグラウンドやコートなどに入ることを禁じられていますが、野球の監督は選手交代や投手へのアドバイスなどでフィールドに入ることもあります。
そのため、選手と同じ舞台に立つから服装も同じにする!という慣習から、監督もユニフォームを着用するようになったそうです。もはや当たり前の光景として見ていた監督のユニフォーム姿ですが、歴史的な背景や実務的な理由など、いろんな要素が絡んでいたのには少し驚きでました!!
ほんの小さなところにも疑問を持ち、そして調べる。細かなところに気が付き、考える力が身につく。名古屋オーシャン野球教室の生徒たちに、そんな風になってほしいとおもっています。
“メジャーリーグにはスーツ姿で指揮をとる監督がいた”

ここまでは、野球の監督がユニフォームである理由を考察してきましたが、逆にユニフォーム以外の服装で指揮を執った監督はいないのか?という疑問をもつ方もいるのではないでしょうか。
実はメジャーリーグにおいて、スーツ姿で指揮を執った監督がいます!!しかも、50年もの長きに渡ってしていたのです。
その人物の名は、コニー・マックといいます。1894年から3年間、ピッツバーグ・パイレーツで選手兼監督を務めたのち、1901年に創設したばかりのフィラデルフィア・アスレチックス(現・オークランド・アスレチックス)の監督に就任しました。その後、1950年までの50年間スーツ姿で指揮を執りつづけ、9回のアメリカンリーグ制覇と5回のワールドシリーズ制覇を達成している名監督なんです!もちろん、当時もユニフォーム姿の監督ばかりでしたが、コニー・マックはとても細身であり、ユニフォームが似合わないと考えたためスーツで指揮を執ることにしたらしいです。
ちなみに、コニー・マックは1934年(昭和9年)には日米野球でアメリカ側の監督として来日しており、ベーブ・ルースやルー・ゲーリッグなどの名選手を率いて日本との試合に臨んでいます。
なお、メジャーリーグでは、コニー・マック以外にスーツ姿で指揮を執った監督はいないとのことです。細身で長身の老紳士といった風貌のコニー・マックのスーツ姿を見たら、他の監督はスーツ姿での采配に二の足を踏むのもかもしれませんね。
こんなに素晴らしい名監督を知らないなんて、いかに選手ばかり注目していたのかが分かりますね。しかも唯一のスーツ監督なのに。
まとめ
野球の監督がユニフォーム姿なのには、意外と納得の理由がありましたね。
たしかに、スーツ姿でノックする監督やコーチは違和感しかないですよね。もはや監督のユニフォーム姿は野球文化といってもいいのではないでしょうか。とはいえ、たまにはビシッとしたスーツ姿で采配を振るう監督が出てきてもいいのではないかとも思います。最近では若い監督も増えてきました。話題になり、野球人気を盛り上げることになってくれれば嬉しいです。
名古屋オーシャン野球教室のコーチがスーツを着て指導していたらおかしいですね。一度見てみたい気もしますが、実現するかは皆さんの目安箱次第です!!