現在新型コロナウイルスが流行っています。
日本、愛知県にもついに新型コロナウイルスが出てしまいました。
ヒトからヒトに感染するということで、マスクを着けた人が多くなってきました。
名古屋オーシャン野球教室に通う子も、帰ったら手洗いうがいを正しく行って予防しましょう。
今日は感染症の研究に尽力した、あの人について取り上げていきます。
千円札のあの人!!!

千円札に書かれている人の名前を知っていますか?
誰しもが知っていますね!
野口英世(のぐちひでよ)という歴史人物です。
お札にのる人は凄い人、つまり偉人なのですが、具体的にどんなことを成し遂げた人なのかわかりますか??
お医者さんとして、数多くの業績を残したこととして有名な人です!
一体どんな人だったのでしょうか。
野口英世の年表や業績を見ながら、どんな人だったのかを見ていきたいと思います!!
野口英世ってどんな人?

まずは野口英世がどんな人だったのかを、小学生の方皆にもわかるよう、ご紹介します。
野口英世は1876年に生まれ、1928年に51才で亡くなった明治、大正時代の細菌学者です。最近新型コロナウイルスが流行っているので、有難みをすごく感じますね。子供のころは英世ではなく、清作(せいさく)という名前でした。
清作は福島県の田舎のまずしい農家に生まれますが、1才のときに家のいろりで左手に大やけどをして、左手が不自由なまま子供時代を過ごすことになってしまいます。お母さんのシカは、自分の不注意から大やけどをおわせてしまい、左手が不自由になってしまった清作は大人になっても畑仕事をして生活することはできない。なので、しっかり勉強をして自分の道をみつけてほしいと願い、必死にはたらいて清作を小学校へ入学させました。
今の小学校は義務教育ですが、この時代はまだ小学校へ入学できるのはお金持ちの家の限られた子供だけでした。貧しくて、左手も不自由な清作は小学校でもいじめられますが、お母さんのシカはいつも清作を励まして清作も熱心に学んで、10才のころには、先生の代理で授業をする「生長」という役目をまかされるほどになりました。
しかし、小学校を卒業した清作は進学したくても家が貧しくて学費を払うことができなかったのです。
すると小学校の恩師・小林先生が、熱心に学び成績のよい清作をどうしても進学させてやりたいと考え、先生が清作の学費をだして、12才の清作を猪苗代高等小学校へと進学させました。そして15才のときには、今度は友人たちの寄付金によって不自由な左手の手術も受けることができました。
このときの出来事によって清作は大きく人生が変わっていきます。
自分のように苦しむ人を救うことができる医者という仕事に感動した清作は大人になったら医者になることを目指して勉強をつづけ19才のときに東京へ出て、さらに熱心に学んで、20才の若さで医師免許の試験に合格して、医師となります。
21才のときには東京の伝染病研究所に入って、北里柴三郎(きたざとしばさぶろう)博士の教えを受けます。このころ名前を清作から英世にあらためています。23才のときに、アメリカに渡り血清学(けっせいがく)や免疫学(めんえきがく)の研究で注目され、その後も、梅毒(ばいどく)の病原菌スピロヘータの研究や、黄熱病(おうねつびょう)の原因を調べる研究、狂犬病(きょうけんびょう)や小児マヒなどの研究もおこないましたが、51才のときに、アフリカに渡って黄熱病の研究をしているときに、英世自身が黄熱病にかかってしまい、亡くなりました。
田舎の貧しい家に生まれて、左手が不自由になったり、けっして恵まれた子供時代ではない中で、お母さんや、小学校の恩師、友人たちの助けに支えられて、野口英世自身も長い年月、たくさんの努力をかさねて世界的な細菌学者になったんですね。
そして数多の苦しむ人達を救いました。
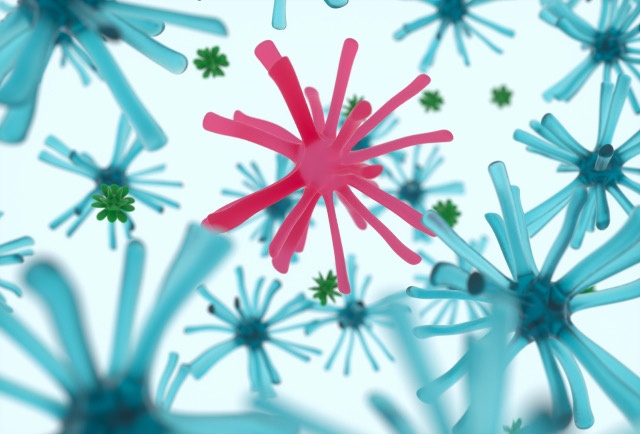
・業績その1
毒蛇(どくへび)の研究
アメリカへ渡った英世はペンシルベニア大学のフレキスナー博士のもとで研究をつづけ、24才のときに毒蛇についての研究発表をします。
これは蛇のもつ毒の性質、あるいは毒蛇にかまれたときにその毒を消すためにどうすればいいかの方法についての研究です。
・業績その2
梅毒(ばいどく)スペロヘータの研究
34才のときには、梅毒という病気の原因であるスペロヘータという細菌を人工的に育てることに成功します。
それまで梅毒は世界中に苦しんでいる人がいるのに、治す方法が知られていない病気でした。
そして、この梅毒を治す方法をみつけるためには、その原因となる細菌をつかった実験が必要でした。
そのため、野口英世がこうした細菌を人工的に育てること成功したことは大きなニュースとなり、世界中にその名前が知られるようになり、ノーベル賞の候補にもなりました。
・業績その3
黄熱病(おうねつびょう)の研究
41才から亡くなるまでの10年間は野口英世は黄熱病の研究にうちこんでいます。
黄熱病とは、蚊にさされることで、ウィルスが人の体の中に入ると、高い熱がでて、体が黄色く変色して、やがて死んでしまうというとても怖い病気です。
英世はこの黄熱病の研究のために、エクアドル、メキシコ、ペルー、ブラジルといった多くの国々を訪れました。しかし51才のときに、アフリカのガーナを訪れていた際に、野口英世自身が黄熱病にかかり亡くなってしまいました。
まとめ

今現在、新型コロナウイルスやインフルエンザといった病気が流行っています。
新型コロナウイルスはSARSを超える死者を出して猛威を振るっています。
野口英世のように研究することはなかなか難しいですが、手洗いうがいをする、マスクをする、人混みを避けるなど出来ることはたくさんあります。
名古屋オーシャン野球教室に通っている皆さんは外での運動になるので、帰ったら手洗いうがいをして自衛していきましょう。

